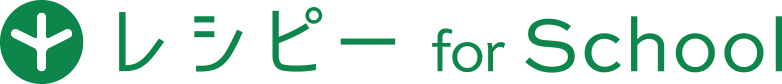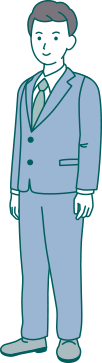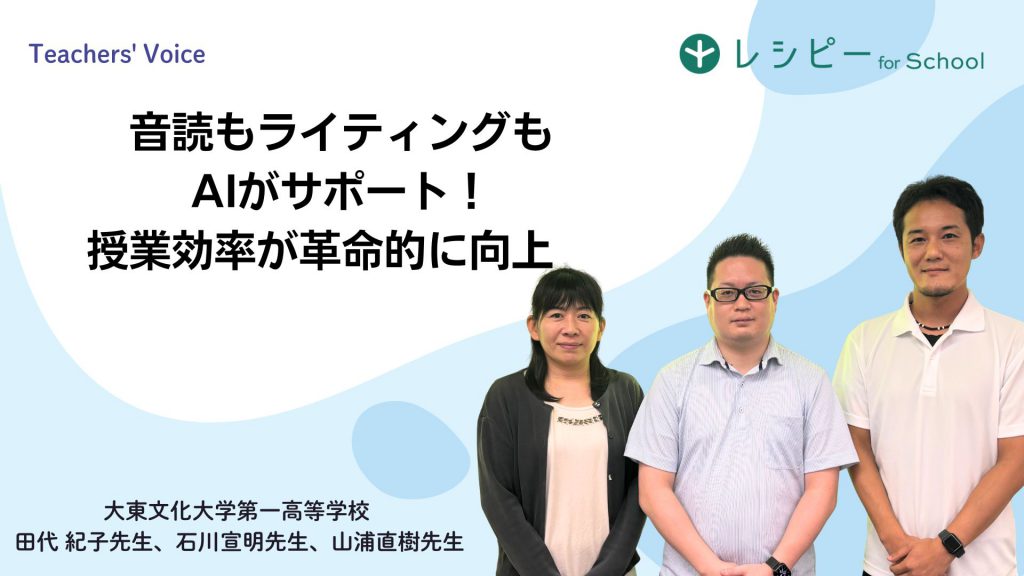
英検の全員受験やカナダ・ニュージーランドの姉妹校との交流など、国際教育にも力を入れている大東文化大学第一高等学校では、2025年度から「レシピー for School」の導入が開始されました。今回は、英語科の石川先生、山浦先生、田代先生に、「レシピー for School」の導入背景や活用の工夫、そして感じている成果についてお話を伺いました。
——貴校はどのような特徴を持つ学校ですか?
山浦先生:大東文化大学第一高等学校には、1学年あたり約350名の生徒が在籍しています。英語教育では「英検」を軸にした指導を行っており、1,2年生は2学期と3学期に自分の選択した級(準2級・準2級プラス・2級)を、3年生は1学期に英検2級を全員受験します。特に3年生では、校内推薦順位を決めるためのテストとして、英検のCSEスコアを採用しています(今年の2年生以降)。そのため、生徒の間でも英検の合格やスコアアップへの意識が高まっています。
——国際教育にも力を入れているそうですね。
山浦先生:はい。毎年10人ほどの生徒が3ヶ月〜1年の長期留学を経験しています。カナダとニュージーランドにある姉妹校との交流も盛んで、2週間の語学研修プログラムを実施しています。海外からの留学生も受け入れており、各クラスで年間1回以上は国際交流の授業を行えるようにしています。国内にいながらの国際交流の機会の多さと英検全員受験は他校ではあまり見られない大きな特徴だと思います。
——現在、どのような英語の授業が行われていますか?
石川先生:本校には「進学」「選抜進学」「特別進学」の3コースがあり、2,3年生ではコースごとに異なる教科書や副教材を使用しています。授業ではシャドーイングやサイトトランスレーションなど、音声を使った練習に力を入れています。また、ネイティブの先生とチームティーチングを行うこともあります。
——従来の英語授業に対して、どのような課題を感じていらっしゃいましたか?
山浦先生:最も大きな課題はライティングの添削でした。授業内で20名ほどの生徒に英文を書かせ、それをすべてチェックして添削するのは非常に大変でした。文法面だけでなく、内容まで踏み込んで修正していたため、1人につき10分ほどかかることもありました。クラスの人数が少ないうちは対応できましたが、40人を超えるクラスでは物理的に不可能でした。
また、定期考査ではiPadなどを使えないため、エッセイライティングの問題を出すことが難しいという課題もありました。以前はネイティブの先生に採点をお願いしたこともありましたが、採点基準の統一などで苦労がありました。
——「レシピー for School」 を導入されたきっかけや背景を教えてください。
石川先生:以前使っていた学習サービスが終了予定となり、英検対策や長期休みの課題配信が難しくなって困っていました。そのタイミングでEDIX(教育サービスの展示会)で「レシピーfor School」を見つけ、導入を検討しました。もともと私が個人向けの「レシピー」を使っていた経験があり、ある程度の使用感が把握できていましたし、学校向けに英検問題の配信機能が追加されると聞いて「これなら安心だ」と感じました。
また、英語の記事や単語学習など幅広い機能があり、課題配信だけでなく、生徒が自分で学べるツールとしても活用できる点に魅力を感じました。
——現在、どのように「レシピー for School」をご利用されていますか?先生お三方の活用方法について教えてください。
石川先生:1年生のクラスでリーディングを中心に使っています。夏休みの40日間、毎日200語程度のリーディング課題と音読課題を出しました。ニュース記事は少し難しいので、自分でカスタムした文章を配信しています。
また、受験クラスでは暗唱例文のテキストを使って「100回音読」の課題を出しました。全ての音声データを管理しているので、生徒の1回目と100回目を聴き比べることができるんです。夏休み明けに実際に音読をさせてみたら、発音やリズムの面でしっかり成長を感じました。
田代先生:3年生は6月に英検の全員受験があったので、1学期はとにかくライティングを中心に取り組みました。英検対策のライティング問題に取り組んでもらい、添削・提出まで行っています。
成績評価にもつながるので、生徒たちも真剣に取り組んでいます。誰がどのくらい書けるのかを把握しやすくなりましたし、スコアをデータで抽出できる点もとても助かっています。
山浦先生:授業の中ではライティングや音読の練習に使っています。夏休みも3回ほど課題を配信しました。音読課題では「85点以上を取らないと提出できない」という設定にしているので、生徒も自然と『85点を超えよう』という意識で練習するようになります。結果的にやる気につながっていると思います。

——サービス導入後、生徒さんたちに変化はありましたか?
石川先生:課題の提出状況がリアルタイムで見えるので、「誰がまだ出していないか」がすぐに分かります。そのおかげで、必要なときにすぐ声をかけたりフォローしたりできるようになって、結果的に提出率も高くなりました。生徒たちも操作にすっかり慣れていて、日常的に使うようになっています。点数がすぐに見えるので、「やらなければ提出できない」という仕組みが自然とモチベーションになっているようです。おかげで学習習慣もしっかり定着してきたと感じます。
——先生方の日々のお仕事についても変化はありましたか?
石川先生:今では、英語の課題はすべて「レシピー for School」の中に集約しています。他教科ではまだ紙ベースでレポートを採点していることが多いのですが、英語科では点数を自動で集計してくれて、それをデータで管理できるので本当に効率的になりました。音読やライティングの課題も、誰がどこまでやっているかがすぐに見えるようになって、大きな変化を感じています。
山浦先生:「レシピー for School」を導入してから、教員の負担が劇的に減りました。特にライティングの添削は「革命的に変わった」と思います。以前は1人ひとりの文章を細かくチェックして、内容まで見て…という作業が本当に大変でしたから。

「レシピー for School」管理画面。生徒が提出した音読の音声・スコアを一括管理できる。
——今後、「レシピー for School」に期待することはありますか?
山浦先生:音読の音声認識や評価の精度がもっと上がったり、ライティングの添削のバリエーションが増えたりすると嬉しいですね。何かあった時もポリグロッツのスタッフさんがこちらの要望にすぐ対応してくださるので、本当に助かっています。今後も協力して、より良い形に進化していけたらいいなと思っています。