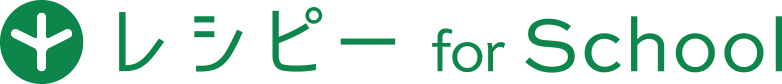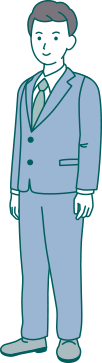——本日は『レシピー for School』を導入いただいている、立命館大学薬学部 教授 の近藤雪絵先生、後藤秀貴講師にお話を伺います。

(立命館大学薬学部教授 近藤雪絵先生)

(立命館大学 後藤秀貴講師)
——立命館大学では「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」という取り組みを行っていると伺いましたが、まずはその内容についてお聞かせいただけますか?
近藤先生:
立命館大学では、薬学部、生命科学部、スポーツ健康科学部、総合心理学部のカリキュラムとして、国際社会で通用する英語発信能力を育成する「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」を実施しています。このプログラムは、学生自身が関心のあるテーマで英語を使って探究・発信することを特徴としており、英語4技能の向上だけでなく、ICTスキルやリサーチスキルの育成にも力を入れています。
——学生さんたちは、どのようなことに興味や関心を持って学ばれていますか?
近藤先生:
PEPでは、 “自分の好きなことを通して学ぶ” という姿勢を大切にしています。学生は、自らの興味や関心を明確にし、それを深く追究する中で、自信を持って社会に発信する力を育んでいきます。自分で設定したテーマをもとに英語で学び、発信することで、学習へのモチベーションが高まり、主体的に取り組もうとする姿勢にもつながっています。
——PEPのような探究的な学びへの導入として、入学前教育で『レシピー for School』をお使いいただきました。導入の背景や決め手をお聞かせいただけますか?
近藤先生:
『レシピー for School』を薬学部の入学前教育に導入しようと考えたのは、PEPと『レシピー』に共通する “学びへの姿勢” に強く共感したからです。PEPでは学生自身の関心に基づいてテーマを選び、主体的に探究・発信することを重視していますが、『レシピー』もまた、 “個別最適化した学習を提供する” という点で非常に親和性が高いと感じました。
特に、「Myレシピ」機能を活用すれば、自分の学びたい技能や関心分野に合わせてコンテンツが配信されるため、学習者一人ひとりの興味に即した学びを実現できます。また、幅広いジャンルの英文記事が揃っており、自然なかたちで英語での情報収集や発信につなげられる点も魅力です。
近年は多くのオンライン英語学習サービスがありますが、どれも “学習者のモチベーション維持や継続率の向上” が課題だと感じています。その中で『レシピー』は、学習への能動的な姿勢を促す仕組みが備わっており、教育現場と協働しながら改善や進化を重ねていける柔軟性もある点に期待を持ちました。
——『レシピー』を利用した入学前教育の学習状況やデータから、学生たちの学びへの姿勢に変化を感じられましたか?
近藤先生:
オンライン学習では、学習者一人ひとりの様子を直接見ながら声をかけることができないため、課題の継続率が課題となりがちです。しかし、今回は課題提出率が非常に高く、印象に残る取り組みとなりました。受講生の満足度も高かったようで、学びへの前向きな姿勢が伺えました。
今回の入学前教育では、「配信課題」「Myレシピ」「自由に記事を読む」という3種類の学習スタイルを用意しました。配信課題はスピーキング問題を中心に構成されており、 “文章を読んだふり” ではなく、自分の声で録音して提出する形式にしたこと、さらに音読スコアに一定の基準を設けたことが、質の高いアウトプットにつながったと感じています。事後アンケートでも、多くの受講生が “スピーキング力が伸びた” と回答しており、自己評価の向上につながったと認識しています。
一方で、個別最適化された学習ができる「Myレシピ」の活用にはばらつきが見られました。せっかくの機能なので、もっと活用してもらえるように、受講生への提示方法や課題との組み合わせ方などに、もう少し工夫の余地があったと思います。
後藤先生:
スマートフォンで気軽に取り組める点も、取り組み率の高さにつながったのではないでしょうか。パソコンを毎日開く習慣がない学習者でも、スマホは毎日手にするので、アクセスのしやすさが継続の後押しになったように感じます。
記事を使った課題も、薬学部を志望する学習者に合わせてテーマや難易度を調整したことで、無理なく“生きた英語”に触れられる良い教材になったと思います。
——『レシピー』のスピーキング課題は、AIによる発音・内容へのフィードバック機能が備わっていますが、この機能についてはどのような印象をお持ちですか?
近藤先生:
AIによるスピーキングフィードバック機能については、受講生も概ね好意的に受け止めていたと思います。私自身大学の授業でもすでに積極的にAIを活用していることもあり、受講生が入学前の段階からその一端に触れられたのは非常に良い経験だったと思います。
後藤先生:
自分の発音に対して細かいフィードバックを受け、何度も繰り返し練習できる機会は、受講生にとって貴重な体験だったと思います。そういった部分が好意的な結果につながったのではないでしょうか。
近藤先生:
ここ数年でAIと学生との距離は大きく縮まっており、今回の取り組みも、そうした流れの中で学生が自然にAIの技術に触れられる機会となりました。大学で今後さらに進んでいくAI活用の入り口としても、十分に意義のある取り組みだったと感じています。
——ポリグロッツのサポート体制や対応について、印象に残っていることがあれば教えてください。
近藤先生:
サポート体制は非常に手厚く、学生一人ひとりにしっかり寄り添ってくださっている印象を受けました。『レシピー』アプリ内のチャット機能を通じて学生が直接問い合わせできる仕組みがあり、サービス提供者との間に“人”としてのつながりを感じられたのは大きかったと思います。また、導入後の途中経過や結果についても丁寧に報告していただき、終始安心して進めることができました。
特に印象的だったのは、入学前に行っていただいた説明会です。担当の方がサービス内容だけでなく、ご自身の経験に基づいて英語学習の意義を直接学生に語ってくださったことで、受講生も “これはAIが提供するものではなく、人が支えているサービスなのだ” と意識しながら前向きに取り組めていたように思います。
後藤先生:
よくある課題として “学習者が何をしているのか先生が把握しきれていない”というケースがありますが、今回は私たちも学生と同じアプリで同じ課題を確認できたため、学習の様子や進行状況を逐一把握できたのが助かりました。
——来年度も引き続き『レシピー for School』をご活用いただけるとのことですが、今後の運用についてお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
近藤先生:
やる気のある学生は、配信課題も「Myレシピ」も楽しんで取り組めていたと思います。だからこそ、なかなかペースをつかめずにいる学習者をどうサポートしていくかが、今後の課題だと感じています。
機能やコンテンツに対する反応は全体的にポジティブでしたが、達成率・継続率はまだまだ向上できると思います。「Myレシピ」は『レシピー』の中でも魅力的なコンテンツの一つだと思うので、より多くの学習者に継続的に活用してもらえるよう工夫を重ねていきたいですね。

(学習者に合わせた一日のカリキュラムをAIが生成して配信してくれる「Myレシピ」。)